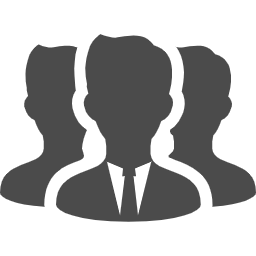貴社のITエンジニアを、技術力と対話力を兼ね備えたハイブリッド人材へ
~「論理と直感」でプロジェクトを成功に導く意思疎通の技法~
このような課題を解決します
- 「技術者と営業・企画部門との意思疎通がうまくいかず、手戻りが多い…」
→ 専門用語に頼らず、相手に伝わる言葉で論理的に説明・提案するスキルを習得します。 - 「チーム内の情報共有が滞りがちで、プロジェクトに遅れが出ることがある…」
→ 円滑な人間関係を築き、報連相を活性化させるための具体的なコミュニケーション手法を学びます。

達成目標
- 【生産性の向上】独力でロジカルに考え、分かりやすく伝える力が身につくため、仕様の誤解や手戻りが減り、開発効率が向上します。
- 【提案力の強化】自信を持って顧客や他部署にプレゼンテーションできるようになり、ビジネスチャンスを拡大します。
- 【組織力の向上】他者と協力して目標を達成するプロセスを学ぶことで、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献できる人材が育ちます。
対象となる受講者様
全階層のIT技術者様
(特に、顧客や他部門との連携、チームでの開発業務において、より高度なコミュニケーション能力が求められる方)
※本研修は、技術者一人ひとりが「自分ごと」として課題に取り組む実践的な内容です。参加される皆様には、「自社やお客様に提案したいこと」を事前に一つ考えていただくようご案内ください。
【前提知識】専門的な前提知識は不要です。
【推奨人数】16名様(人数が超える場合は、効果的な運営方法を別途ご提案しますのでご相談ください)
カリキュラム(オンラインも可能です)
※改善のためカリキュラムは予告なく変更させていただくことがあります。
1日目:論理的思考力と伝達の基礎を固める
| ◎研修の目的と組織貢献への接続【講義】 ・コミュニケーションが組織の成果を左右する理由 ・技術者にとっての論理性がもたらす価値 1.信頼関係を築く技術【講義・演習】 (1)周囲を巻き込む人の共通点 (2)協力を引き出す「お願いの仕方」7か条 (3)円滑な対話を生むクッション言葉 2.ロジカルコミュニケーションの型【演習】 (1)論理とは何か? (2)誰もが納得する論理の基本構造 3.ロジカルシンキングの実践【演習】 (1)思考を整理する4ステップ (2)個人ワーク:業務課題の整理 (3)グループ内発表と多角的なフィードバック 4.思考を深めるフレームワーク【講義】 (1)Why so? So What?による深掘り (2)MECEによる網羅的な視点 (3)人を動かすストーリーの作り方 5.プレゼンテーションの原理原則【講義】 (1)なぜ、プレゼンは重要か? (2)聞き手を動かす3つの要素(3C) (3)論理的なプレゼンテーションの構成法 |
2日目:実践的なプレゼンテーションで応用力を磨く
| 6.聞き手の心を掴む導入スキル【演習】 (1)自己紹介で惹きつける (2)意外な数値データで興味を引く (3)クイズ形式で参加を促す 7.目的に応じた本論の構成【演習】 (1)事実を正確に伝える「説明型」 (2)意見を明確に主張する「主張型」 (3)行動を促す「提案型」 8.実践!プレゼンテーション企画【グループ演習】 ・実際の業務を題材に、プレゼンテーションプランを作成 ・ドキュメント作成とレビュー ・講師による個別フィードバック ・本番を想定したリハーサルと相互フィードバック 9.プレゼンテーション本番と学びの定着【演習】 ・個別発表(VTR収録による客観的分析も可能です) ・講師からの総評とフィードバック ◎総まとめ ・明日からの業務に活かすためのアクションプラン策定 |
研修費用
※貴社へお伺いする場合、名古屋市内からの交通費・宿泊費が別途発生する場合がございます。
講師料:300,000円(税別)
※受講者16名様まで講師1名で対応。人数に応じて最適な体制をご提案します。
テキスト代:3,000円(税別)× 参加人数
※本研修は、人材開発支援助成金の対象となる場合がございます。申請に関するご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
イメージ写真


高いエンゲージメントと実践効果の証明:受講者様の声
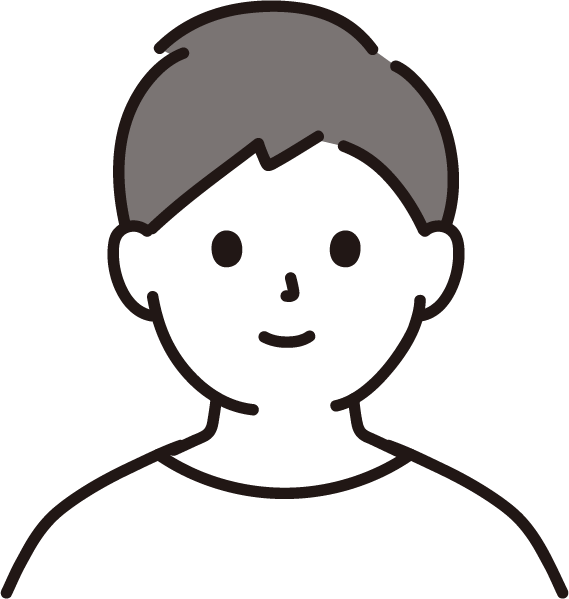
ワークがたくさん用意してあり、楽しみながら受講することができました。
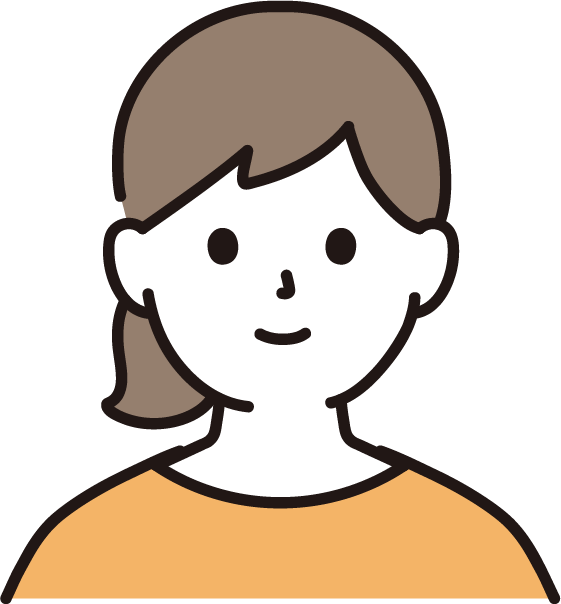
実践が多く、インプットした内容をアプトプットとして活かせてよかったです。P・PREP法が非常に有効だと実感しました。3日間ありがとうございました。久しぶりの研修で楽しく受講できました。また、機会があればよろしくお願いします。
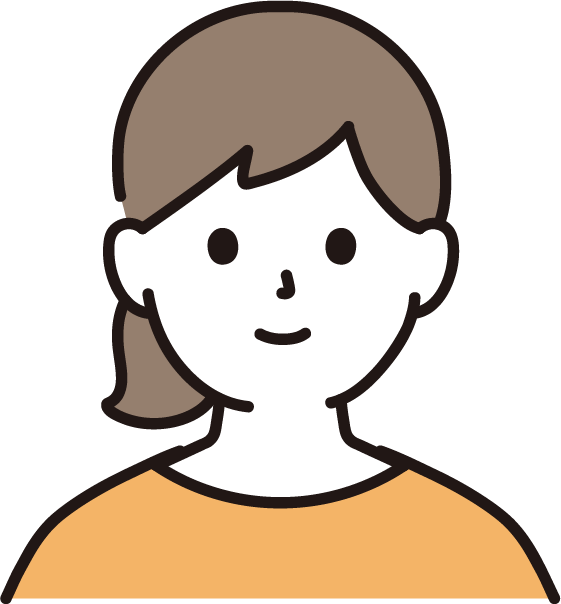
演習や発表が多かった為、発言が多くできてよかった。
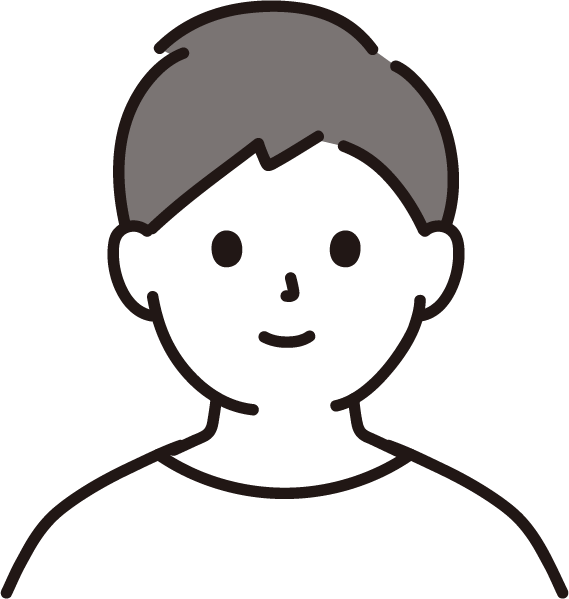
ワークが中心の研修だったので、退屈せずに学ぶことができた。皆さんの前で発表する機会が多かったので貴重な経験になった。3日間楽しく受講できました。ありがとうございました!!
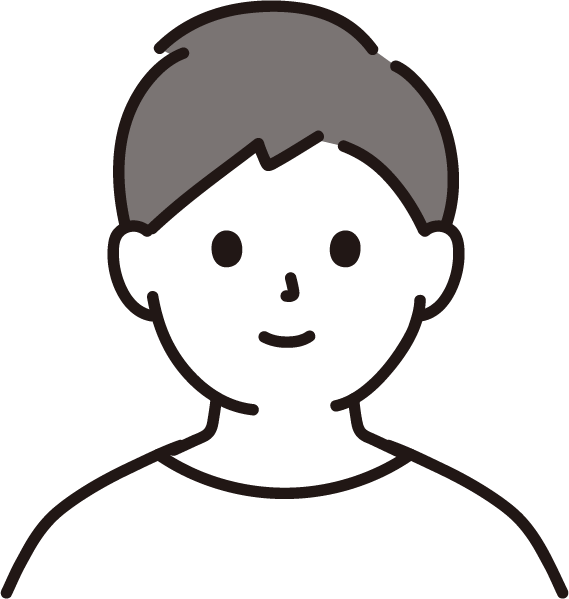
前に出て発表する機会が多かったので、緊張しましたが、自信を持って発表できました。
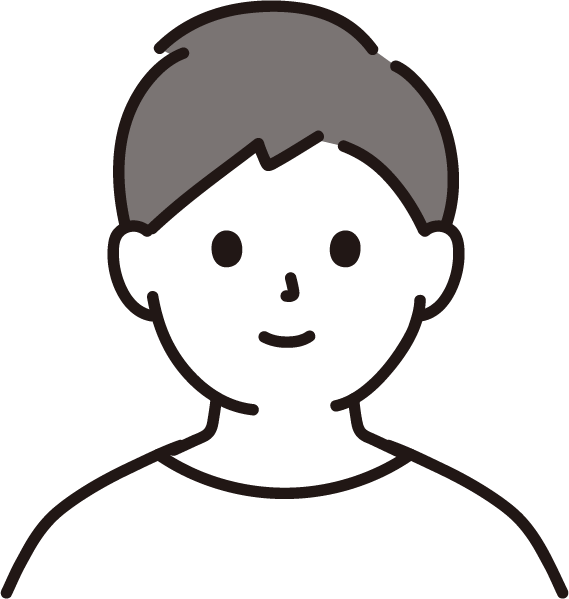
発表など実践できてよかったです。3日間ありがとうございました。
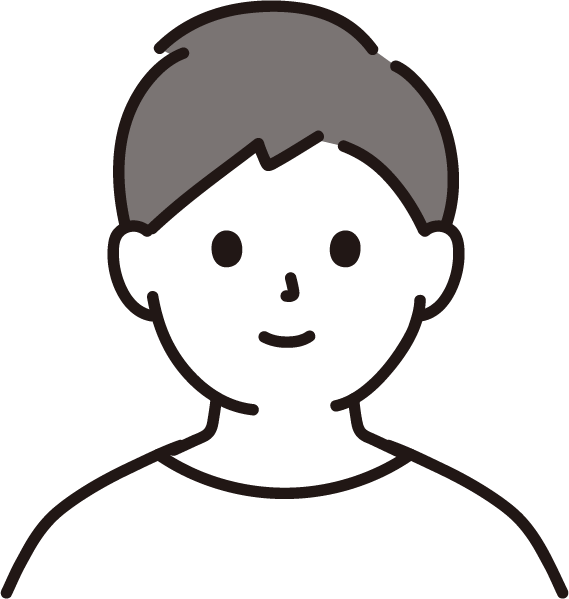
グループワークを取り入れていたので、他者の意見を聞く機会を多く持つことができました。
このページを見ている方にオススメの研修
IT企業の人財育成に関することなら受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ メールでお気軽にどうぞ