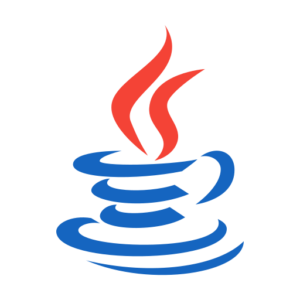【初心者エンジニア向け】アフォーダンスとは?日常とUIデザインで役立つ心理学的ヒント!
こんにちは。ゆうせいです。
今日は、新人エンジニアの方にぜひ知っておいてほしい「アフォーダンス」という考え方について、わかりやすくお話しします!
この言葉、聞き慣れないかもしれませんが、UI/UXデザインやプロダクト設計、さらには日常生活にも深く関係する非常に重要な概念なんです。
アフォーダンスとは?ざっくり言うと…
アフォーダンス(affordance) とは、「ある物体が、どんな行動をとれるかを自然に示す性質」のことです。
もっと簡単に言うと、「見ただけで、どう使うかがわかる仕組み」と考えてください!
例えで理解しよう!
たとえば、ドアを思い浮かべてください。
- ドアノブがついていたら、「回すんだな」と感じますよね?
- 押し板がついていたら、「押すんだな」と自然にわかります。
これは、形やデザインが「こう使ってください」と無言で教えてくれているのです。これこそがアフォーダンスです!
アフォーダンスの起源と定義
アフォーダンスは、心理学者ジェームズ・J・ギブソンが1970年代に提唱した概念です。もともとは人間の知覚に関する理論で、「環境が人に与える行動のきっかけ(= afford)」という意味合いでした。
後に、ドナルド・ノーマンという認知科学者がこの概念をUIやデザインに応用しました。
ノーマン的アフォーダンス(知覚可能なアフォーダンス)
- 「使い方が目で見てわかる」
- デザインによって正しい操作を誘導できる
というのがポイントです。
UIデザインにおける活用例
ボタンのデザイン
- 立体的に見えるボタン → 「押せそう」
- カーソルを当てたら色が変わる → 「クリックできるとわかる」
スクロールの誘導
- コンテンツの下にちょっとだけ次の要素が見えている → 「下にスクロールできそう」と感じる
これらはすべて、ユーザーが迷わずに操作できるよう、アフォーダンスを意識したデザインになっています。
メリットとデメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ユーザーが直感的に操作できる | アフォーダンスが過剰だと逆に混乱を招くことも |
| 操作マニュアル不要で使いやすくなる | デザインに制限が出る場合もある |
物理的アフォーダンス vs デジタルアフォーダンス
| 種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 物理的アフォーダンス | 実物の形や材質が示す使い方 | ドアノブ、取っ手、椅子の形 |
| デジタルアフォーダンス | UIやアイコンが示す使い方 | ボタンの影、カーソル変化、リンクの色 |
たとえば「下線付きの青い文字」は、たいてい「リンクだ」と理解されます。これも、ネット時代に育まれたアフォーダンスの一種です。
アフォーダンスとサイン(signifier)の違いは?
ノーマンは、サイン(signifier)という言葉も紹介しています。
- アフォーダンス=「行動できる可能性」
- サイン=「その可能性があることを示すもの」
つまり、「ドアノブを見て、回せるとわかる」→ サインがアフォーダンスを伝えているという構造です!
図解で理解しよう!
アフォーダンスの関係図
[物の形] → [人の直感] → [行動]
↑ ↓
サイン(signifier)
なぜエンジニアが知っておくべき?
エンジニアも、ただ機能を実装するだけでなく、
- 「ユーザーはどう感じるか?」
- 「この操作は直感的か?」
を考える必要があります。
アフォーダンスを意識すれば、ユーザーが迷わないプロダクトを作れます!
まとめ
- アフォーダンスとは「使い方を自然に伝える性質」
- UIデザインでも超重要
- ユーザーが操作を間違えにくくなる
- サイン(signifier)とセットで考えると理解しやすい
今後の学び方
次のステップとしては、以下のような学びがおすすめです!
- ノーマンの著書『誰のためのデザイン?』を読む
- 自分がよく使うアプリの中で「アフォーダンス」がどう活かされているか観察する
- 自分で簡単なUIを作り、「自然に操作できるか?」をユーザーに聞いてみる
それでは、楽しい学習を!
投稿者プロフィール

- 代表取締役
-
セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
すべての無駄を省いた費用対効果の高い「筋肉質」な研修を提供します!
この記事に間違い等ありましたらぜひお知らせください。
学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。
最新の投稿
 新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの? コピー
新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの? コピー 新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの?
新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの? 新人エンジニア研修講師2026年2月28日AIの深層へようこそ!逆伝播バックプロパゲーションの仕組みを完全マスター
新人エンジニア研修講師2026年2月28日AIの深層へようこそ!逆伝播バックプロパゲーションの仕組みを完全マスター 新人エンジニア研修講師2026年2月28日機械学習で必須のscikit-learn関数ベスト10
新人エンジニア研修講師2026年2月28日機械学習で必須のscikit-learn関数ベスト10