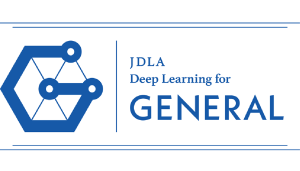「混同行列」という名前の由来は?なぜそんな呼び方をするのかを解説!
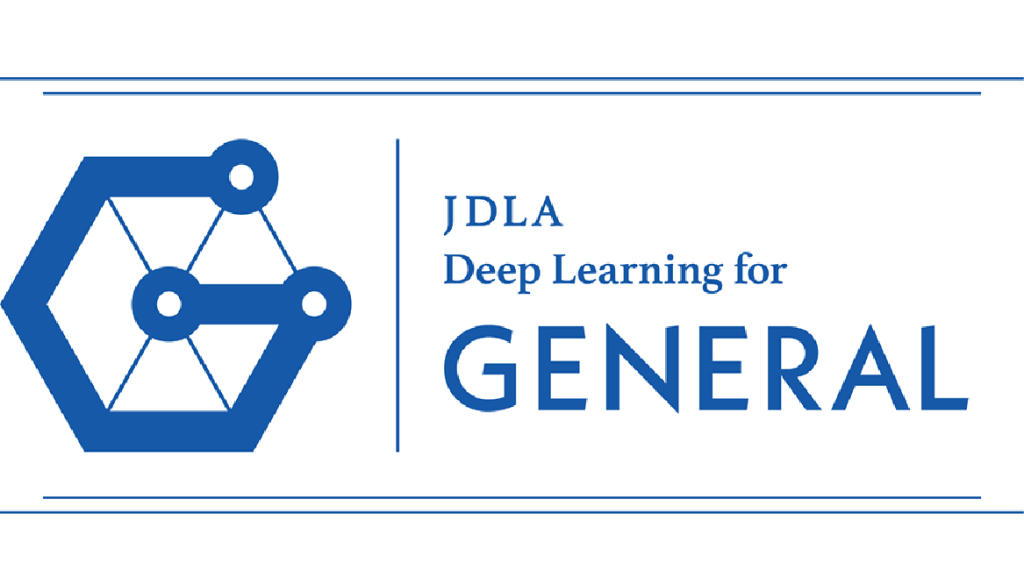
こんにちは。ゆうせいです。
「混同行列(こんどうぎょうれつ)」って、ちょっと不思議な名前だと思いませんか?
たとえば「正解表」や「誤判定マトリクス」みたいな名前でもよさそうなのに、なぜわざわざ“混同”という言葉を使うのか?
この言葉には、分類モデルの本質的な弱点をついた鋭い意味が込められているんです。
今回はその由来と意味をわかりやすくお話しします!
「混同行列」という名前の意味とは?
「混同」ってどういうこと?
まず、日常の言葉として「混同する」とは、2つの異なるものを取り違えることを意味します。
たとえば:
- AさんとBさんを混同した
- 正義と自己満足を混同している
つまり、「本当は違うのに、同じだと思ってしまうこと」ですよね。
では、分類モデルは何を混同するのか?
答えは明快です:
「実際のクラス(正解)」と「モデルが予測したクラス(予測)」を混同すること
つまり、混同行列とは、
分類モデルが“混同した回数”を数え上げる表
なんです。
表で見てみよう(例:病気判定)
| 病気と予測 | 健康と予測 | |
|---|---|---|
| 実際は病気 | 真陽性(TP) | 偽陰性(FN) |
| 実際は健康 | 偽陽性(FP) | 真陰性(TN) |
ここでの「混同」は次の2つ:
- FP(偽陽性):健康な人を病気と間違えた(健康と病気を混同)
- FN(偽陰性):病気の人を健康と見なした(逆の混同)
つまり、「混同行列」はこの2つの“取り違え”を視覚的に整理するための表なんです。
なぜ「間違い」じゃなくて「混同」なの?
ここでのポイントは、「分類ミス」というよりも「分類の取り違え方」に焦点があるという点です。
- 「どのクラスをどのクラスと取り違えてしまったか?」
- 「どのパターンで混乱が起きやすいか?」
たとえば:
- ネコをイヌと間違えるのか?
- イヌをネコと間違えるのか?
- ライオンをネコと誤分類するのか?
こうした誤分類のパターンの傾向=混同の構造を明らかにするのが、混同行列です。
英語でも “Confusion Matrix” と呼ばれる
ちなみに「混同行列」は英語でそのまま Confusion Matrix です。
confusion = 混乱、混同、取り違え
つまり、もともと英語圏でも「分類の混乱ぶりを表にしたもの」というニュアンスがあります。
この英語表現を日本語に直訳したのが「混同行列」なんですね。
名前の意味を一言でまとめると?
混同行列=モデルが「何と何を間違えたか」を分類ごとに整理した表
まとめ:なぜ「混同行列」という名前なのか?
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 「混同」とは? | 異なるものを取り違えること |
| 何を混同する? | 実際のクラスと予測クラス |
| なぜ重要? | モデルの“誤認の傾向”を具体的に把握できる |
| 英語の由来 | Confusion Matrix(同じ意味) |
| 意味すること | 分類モデルの性能をただの精度ではなく、「どのように間違えたか」という構造で示す |
今後の学習の指針
混同行列の意味をしっかり理解したら、次は次のステップへ!
- 混同行列から導ける評価指標:精度(accuracy)・適合率(precision)・再現率(recall)・F1スコア
- クラスの不均衡に強い指標(例:PR曲線やROC曲線)
- 多クラス分類(3つ以上のラベル)での混同行列の扱い方
機械がどう「混乱するか」を知ることで、逆に「どこを改善すべきか」が見えてきます!
ぜひあなたの分析力に活かしてみてくださいね。
生成AI研修のおすすめメニュー
投稿者プロフィール

- 代表取締役
-
セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
すべての無駄を省いた費用対効果の高い「筋肉質」な研修を提供します!
この記事に間違い等ありましたらぜひお知らせください。
学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。
最新の投稿
 新人エンジニア研修講師2026年2月26日機械学習の文字式・記号お約束のまとめ
新人エンジニア研修講師2026年2月26日機械学習の文字式・記号お約束のまとめ 新人エンジニア研修講師2026年2月26日逆三角形の魔法?機械学習で絶対つまずくナブラとデルタの超簡単な覚え方
新人エンジニア研修講師2026年2月26日逆三角形の魔法?機械学習で絶対つまずくナブラとデルタの超簡単な覚え方 新人エンジニア研修講師2026年2月26日プログラミング初心者が最初に知るべきYAMLの基本
新人エンジニア研修講師2026年2月26日プログラミング初心者が最初に知るべきYAMLの基本 新人エンジニア研修講師2026年2月26日バラバラのデータを一つに!numpyの配列結合(concatenateとvstack)をマスターしよう
新人エンジニア研修講師2026年2月26日バラバラのデータを一つに!numpyの配列結合(concatenateとvstack)をマスターしよう