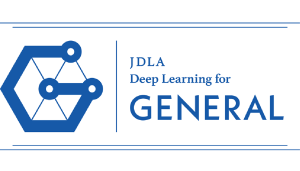【新人エンジニア向け】モデルの「実力」どう測る?残差、汎化誤差、MAE、MSEの違い
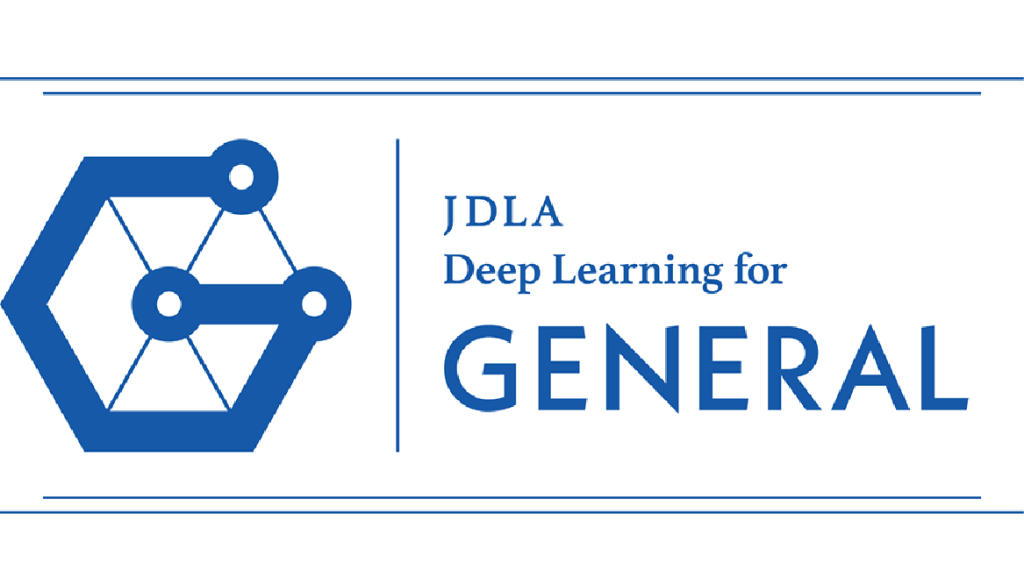
こんにちは。ゆうせいです。
一生懸命に機械学習のモデルを作ったはいいけれど、「このモデル、本当に『デキる子』なのかな?」と、その実力をどうやって測ればいいか、悩んでいませんか?
モデルの性能を評価するとき、私たちは必ず「誤差(ごさ)」というものさしを使います。
この「誤差」、つまり「予測と現実のズレ」には、実はいくつか種類があり、測り方にも違いがあるんです。
今日は、新人エンジニアのあなたにぜひ知っておいてほしい、基本的な誤差の種類について、一つずつ丁寧に解説していきますね!
モデル評価の基本!「誤差」とは?
まず大前提として、誤差とは「モデルが予測した値」と「実際の値(実測値)」とのズレのことを指します。
例えば、モデルが「明日の来客数は100人」と予測したのに、実際は「105人」だった場合、この「5人」が誤差です。
この誤差をどう扱うかが、評価のキモになってきます。
誤差は「どこで」測る?
一口に誤差と言っても、「どのデータを使って測ったズレなのか?」によって、その意味合いが大きく変わってきます。
1. 残差(ざんさ)
これは、モデルを作るために使ったデータ(=手元の学習データ)での誤差のことです。
- イメージ: 勉強に使った「練習問題集」での答え合わせ。
- 特徴:モデルは、この「残差」をできるだけ小さくするように一生懸命に学習します。そのため、学習が進めば進むほど、残差は小さくなる傾向があります。
- 注意点:残差が小さいからといって、喜ぶのはまだ早い!モデルが練習問題の「答えを丸暗記」してしまっただけ(これを過学習と言います)かもしれません。丸暗記したモデルは、見たことのない「本番の試験」では全く点が取れないですよね。
2. 真の誤差(汎化誤差・テスト誤差)
これこそが私たちが本当に知りたい、モデルがまだ一度も見たことがない「未知のデータ」に対する誤差のことです。
- イメージ: 練習問題集ではなく、「本番の試験」での成績。
- 特徴:この誤差が小さいモデルほど、「未知のデータに対しても、ちゃんと予測できる」優秀なモデル、つまり汎化(はんか)性能が高いモデルだと言えます。この真の誤差そのものを知ることはできないため、手元のデータを分割して作った「テストデータ」で測定したテスト誤差を、その代わりとして使います。
ズレを「どう」測る?
では、個々のデータで発生した「+5のズレ」や「-3のズレ」を、どうやって一つの評価値にまとめればよいでしょうか?
その計算方法にも種類があります。
1. 絶対誤差
これは、誤差の「大きさ」だけに着目した測り方です。
プラスかマイナスかは無視します。
- 計算: 誤差が「+5」でも「-5」でも、絶対誤差は「5」となります。
- 使われ方:この絶対誤差を、すべてのデータについて平均したものが MAE (Mean Absolute Error: 平均絶対誤差) です。MAEは「平均すると、だいたいこれくらい予測がズレるんだな」と直感的に理解しやすいのがメリットです。
2. 二乗誤差
これは、誤差を「2乗(同じ数を2回かける)」した測り方です。
- 計算:
- 誤差が「+5」なら
- 誤差が「-5」でも
- 誤差が「+2」なら
- 誤差が「+5」なら
- 特徴:この計算方法のすごいところは、「大きなズレ」をより重く罰する(ペナルティを与える)点です!誤差「5」は25になりますが、誤差「2」は4にしかなりません。「予測をちょっと外すのは許すけど、ものすごく大きく外すのは絶対にダメ!」という場合に適しています。
- 使われ方:この二乗誤差の平均が MSE (Mean Squared Error: 平均二乗誤差) です。さらに、MSEの平方根(ルート)を取って単位を元に戻したものが RMSE (Root Mean Squared Error: 二乗平均平方根誤差) です。
今後の学習の指針
さて、今日はモデル評価の基本となる「誤差」の種類についてお話ししました。
- 残差: 練習問題での誤差
- 汎化誤差(テスト誤差): 本番の試験での誤差
- 絶対誤差: ズレの大きさをそのまま評価(→ MAE)
- 二乗誤差: 大きなズレを厳しく評価(→ MSE, RMSE)
という違いがあることを、まずはしっかり押さえてください。
次に学ぶステップとしては、今日登場した「MAE」と「RMSE」のどちらを評価指標として選ぶべきか?を考えてみると良いでしょう。
「外れ値(極端に大きい誤差)の影響をどう考えるか?」が、使い分けの大きなヒントになりますよ。
モデルの「クセ」を見抜き、その実力を正しく評価できるよう、一歩ずつマスターしていきましょうね!
この基本をしっかり押さえておくことで、今後の学習がグッと楽になりますよ。
生成AI研修のおすすめメニュー
投稿者プロフィール

- 代表取締役
-
セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
すべての無駄を省いた費用対効果の高い「筋肉質」な研修を提供します!
この記事に間違い等ありましたらぜひお知らせください。
学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。
最新の投稿
 新人エンジニア研修講師2026年2月28日初心者が選ぶべき道しるべ!データ分析の魔法「クラスタリング」完全ガイド
新人エンジニア研修講師2026年2月28日初心者が選ぶべき道しるべ!データ分析の魔法「クラスタリング」完全ガイド 新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの?
新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの? 新人エンジニア研修講師2026年2月28日AIの深層へようこそ!逆伝播バックプロパゲーションの仕組みを完全マスター
新人エンジニア研修講師2026年2月28日AIの深層へようこそ!逆伝播バックプロパゲーションの仕組みを完全マスター 新人エンジニア研修講師2026年2月28日機械学習で必須のscikit-learn関数ベスト10
新人エンジニア研修講師2026年2月28日機械学習で必須のscikit-learn関数ベスト10