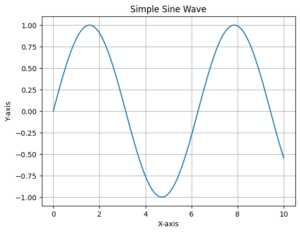【サービス別】生成AIの生成物の権利はどうなる?
こんにちは。ゆうせいです。
「このAIが作ったイラスト、かっこいいから自社のブログで使いたいな」
「ChatGPTに出力させた文章を、そのまま製品のキャッチコピーにしていいんだろうか?」
生成AIが急速に普及する中で、こんな風に「これって誰のもの?」という著作権に関する疑問を感じる場面が増えてきたのではないでしょうか。特に、ビジネスで利用するとなると、権利関係は絶対に無視できない問題ですよね。
今回は、この複雑で少し難しい「生成AIと著作権」の問題について、現在の日本の法律の考え方と、皆さんがよく使うであろう主要なサービスが、利用規約でどのように定めているのかを、分かりやすく解説していきます!
そもそも、AIの生成物に「著作権」はあるの?
本題に入る前に、日本の著作権法の基本的な考え方をおさらいしましょう。
日本の法律では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。そして、その作り手である「著作者」は、基本的に「人間」であることが前提となっています。
この考え方に従うと、AI自体が著作者になることは、現時点では認められていません。
では、AIを使って何かを生成した場合、その著作権は誰のものになるのでしょうか?
ここで重要になるのが、「人間の創作的寄与」があったかどうか、という点です。つまり、AIを単なる「道具」として使い、生成プロセスに人間がどれだけ創造的な工夫を加えたか、が問われるのです。
例えば、簡単な単語をいくつか入力しただけ(簡単なプロンプト)で、あとはAIが自動で生成した、という場合は、「人間の創作的寄与」は無いと判断され、誰の著作物でもない(著作権が発生しない)可能性が高いと考えられています。
【サービス別】生成物の権利はどうなる?規約を比較してみよう
法律の考え方は分かりましたが、それとは別に、私たちがサービスを使う上でのルールである「利用規約」もしっかりと確認する必要があります。サービスごとに権利の扱いが異なるため、ここを理解しておくことが非常に重要です!
主要な生成AIサービスについて、規約のポイントを表にまとめてみました。
| サービス名 | 生成物の権利の帰属 | 商用利用 | 特に注意すべき点 |
| OpenAI (ChatGPT, DALL-E 3) | ユーザーに譲渡される | 可能 | 生成物の責任は全てユーザーにある。他者の権利を侵害しないこと。 |
| Midjourney | 有料会員:ユーザー 無料会員:なし | 有料会員:可能 無料会員:不可 | 無料版での生成物は公開され、誰でも利用できるライセンスが付与される。 |
| Stable Diffusion (Stability AI) | ユーザーに帰属 | 可能 | 利用するモデルやプラットフォームのライセンスを個別に確認する必要がある。 |
| Gemini (Google) | ユーザーに帰属 | 可能 | サービス改善のため、Googleが入力・生成コンテンツを利用する場合がある。 |
| Microsoft Copilot | ユーザーに帰属 | 可能 | Microsoftのサービス規約が適用される。著作権侵害で訴えられた場合に保護するプログラムがある。 |
※2025年10月時点の情報です。規約は頻繁に更新されるため、必ず公式サイトの最新の利用規約を直接確認してください。
OpenAI (ChatGPT, DALL-E 3)
規約上、生成した文章や画像の権利は、原則としてユーザーに譲渡されます。そのため、商用利用も可能です。ただし、これは「OpenAIが権利を主張しない」という意味であり、生成物が他者の著作権を侵害していないことまで保証するものではありません。最終的な責任は利用者にあります。
Midjourney
プランによって扱いが大きく異なるのが特徴です。有料プランのユーザーは生成した画像の所有権を持ち、商用利用もできます。一方、無料プランで生成した画像は、誰でも自由に利用・改変できるライセンス(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)が付与され、公開されます。ビジネスで使うなら、有料プランが必須と言えるでしょう。
Stable Diffusion
オープンソースをベースにしているため、比較的自由度が高いのが特徴です。生成した画像の権利は基本的にユーザーのものとなり、商用利用も可能です。ただし、学習に使われているモデルによっては、特定の条件(クレジット表記など)が定められている場合があるため、利用するモデルごとのライセンス確認が不可欠です。
Gemini (Google) & Microsoft Copilot
これらはOpenAIと同様に、生成物の権利はユーザーに帰属し、商用利用も可能、というスタンスです。特にMicrosoftは、同社のCopilotを使って生成したコンテンツが原因で著作権侵害の訴訟を起こされた場合に、ユーザーを法的に保護する「Copilot Copyright Commitment」というプログラムを発表しており、ビジネス利用における安心材料の一つとなっています。
新人エンジニアが本当に注意すべきこと
各サービスの規約が分かったところで、最後に、エンジニアとして必ず心に留めておくべき注意点をまとめます。
1. 「規約でOK」と「法的にOK」はイコールではない
最も重要な心構えです。サービスの規約で商用利用が許可されていても、生成したものが、たまたま既存のキャラクターやデザインにそっくりだった場合、意図せず著作権侵害になってしまうリスクは常に存在します。生成物は必ず自分の目で確認し、何かに酷似していないかチェックする癖をつけましょう。
2. 入力する情報に細心の注意を払う!
サービスによっては、入力したプロンプトやデータを、AIの再学習に利用することがあります。会社の機密情報、個人情報、そしてまだ公開していないソースコードなどを絶対に入力してはいけません。情報漏洩の入り口になる危険性を常に意識してください。
3. 最終的な責任は「あなた」にある
AIはあくまで道具です。その道具を使って生み出したものによって、もし何らかのトラブルが発生した場合、その責任を負うのはAIやサービス提供者ではなく、利用者である「あなた自身」です。この当事者意識を持つことが、リスクを避けるための第一歩となります。
まとめと今後の学習指-針
生成AIと著作権を取り巻く環境は、まだ発展途上にあり、法律や社会のルールがこれから整備されていく段階です。現時点では、明確な答えがない「グレーゾーン」が多いことも事実です。
だからこそ、私たちエンジニアに求められるのは、「サービスの利用規約を、必ず一次情報として自分で確認する」という基本姿勢です。
今回ご紹介した内容をきっかけに、ぜひ一度、自分が使っているサービスの利用規約に目を通してみてください。そして、AIと法律に関するニュースにもアンテナを張っておきましょう。技術の進化とともにルールも変わっていきます。その変化に追従していくことが、これからのエンジニアにとって不可欠なスキルとなるはずです。
セイ・コンサルティング・グループの新人エンジニア研修のメニューへのリンク
投稿者プロフィール

- 代表取締役
-
セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
すべての無駄を省いた費用対効果の高い「筋肉質」な研修を提供します!
この記事に間違い等ありましたらぜひお知らせください。
学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。
最新の投稿
 新人エンジニア研修講師2026年2月28日初心者が選ぶべき道しるべ!データ分析の魔法「クラスタリング」完全ガイド
新人エンジニア研修講師2026年2月28日初心者が選ぶべき道しるべ!データ分析の魔法「クラスタリング」完全ガイド 新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの?
新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの? 新人エンジニア研修講師2026年2月28日AIの深層へようこそ!逆伝播バックプロパゲーションの仕組みを完全マスター
新人エンジニア研修講師2026年2月28日AIの深層へようこそ!逆伝播バックプロパゲーションの仕組みを完全マスター 新人エンジニア研修講師2026年2月28日機械学習で必須のscikit-learn関数ベスト10
新人エンジニア研修講師2026年2月28日機械学習で必須のscikit-learn関数ベスト10