時短・効率化だけじゃない!社員が自ら動き出すDXの始め方
はじめに:なぜ「遅れ」が問題になるか
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なるIT化・デジタルツールの導入ではなく、「業務・組織・ビジネスモデルをデジタル技術を軸に根本変革すること」を指します。
もしDXの取り組みが遅れてしまうと、以下のような弊害が生まれます:
- 競合他社に後れをとる
- コスト構造が劣化する(旧来業務の非効率さを引きずる)
- 人材(特に若手、デジタル志向者)を惹きつけにくくなる
- 顧客期待・市場変化に対応できない
こうしたリスクを理解したうえで、「なぜ遅れるのか」「まずどこに手をつけるべきか」を考えておかないと、DXは“絵に描いた餅”になってしまいます。
私たち人材育成会社の視点では、“人”の側をどう育て、巻き込むかが成否を決める大きな要因になります。その点も意識しながら進めていきましょう。
DX推進が遅れる主な原因(障壁)
まず、なぜDXが後手になるのか、典型的な原因を整理します。これは多くの企業で見られるもので、「あなたのクライアント企業にも当てはまるかも…」と感じていただければと思います。
| 障壁カテゴリ | 具体的な課題 | なぜそれが遅れにつながるか |
|---|---|---|
| 技術・システム面 | レガシーシステム依存、システム間の非連携、データのサイロ化 | 古いシステムは改修が難しく、新しい技術との結合性が低い。切り替えリスクを怖がる。 |
| 人材・スキル面 | デジタル人材の不足、既存社員のデジタルリテラシー不足 | 必要なスキルをもつ人材が社内に少ない。教育コスト/時間がかかる。 |
| 組織・文化面 | 縦割り部署、部門間協業の欠如、失敗を嫌う文化、変化抵抗 | 部門間で連携できないと横断型プロジェクトが動かない。新しいやり方に抵抗が強い。 |
| 経営層・意思決定面 | 経営層のコミットメント不足、意思決定の遅さ、DXへの理解ギャップ | 現場が動きたくても、予算や承認が下りず停滞する。 |
| 制度・規制・外部環境 | 法規制、業界固有の制約、情報セキュリティ・プライバシー要件 | 特定業界(金融、医療、公共など)は法制度の制約が強いため、自由にデータを動かしにくい。 |
| 優先順位・リソース配分 | DX以外の「日常運営・短期課題」が優先される | 緊急性のある業務対処に追われ、DX投資が後回しにされる。 |
たとえば、「既存システムを変えると業務停止リスクが出るから怖い」「DX投資に即効性が見えないから後回し」などの心理もここに含まれます。こういう“見えない抵抗”が実は重いんです。
日本企業における典型例として、レガシーシステムの維持がDXの足かせになるという指摘がよくなされており、経済産業省も“2025年の崖”という言葉で警鐘を鳴らしています。
また、組織文化・意思決定プロセスの硬直性も大きな壁という声も目立ちます。
IT企業向け人材育成会社視点で見る「遅れ」の原因の切り口
少し観点を変えて、「人材育成会社」という立場から、なぜ顧客企業でDXが遅れるかを“学び・育成”視点で整理します。
- 変革を担えるリーダー育成が追いつかない
DXプロジェクトをリードできる中間管理職・部門責任者を育てるプログラムがないケースが多い。現場を導く人が不在だと足が止まる。 - 現場社員の抵抗・不安対応が不十分
「自分の仕事が奪われるのでは」「うまく使えるか自信がない」など心理的抵抗が根強い。これをフォローする教育設計が甘い。 - 学習機会・メンタリング体制がない
DXに必要なスキル(データ分析、AI、クラウド、アジャイル開発など)を学べる場がない、もしくは断片的で体系化されていない。 - 教育と実践のギャップ
座学で学んでも、現場で使えない・応用できないという“死んだ学び”になる。OJTやハンズオン実践と繋げないと意味が薄い。 - 成果が見えにくくモチベーション低下
DX投資の成果がすぐに出ないと、「なんでこんなに苦労してるんだ?」という空気が広がる。教育→成果還元の仕組みが弱いと挫折する。
だから、DX遅延を防ぐには、技術整備だけではなく「学びと人を動かす仕組み」をDX戦略に初期から埋め込むことが肝になります。
着手すべき優先順位:どこから手をつけるべきか
DX推進を「どこから始めるか」の判断は、企業の状況・規模・業種・強みなどで異なります。ただし、原則として リスクが小さく成果を出しやすい領域 から始めて、徐々に拡大していく「スモールスタート → 拡張型」アプローチが現実的です。
以下は、優先順位の考え方と典型的なフェーズ例です(人材育成会社視点も交えて)。
優先順位の考え方(評価基準)
DXの着手領域を選ぶ際には、以下の軸を使って優先度を判断するとよいでしょう:
| 評価軸 | 例 | どう使うか |
|---|---|---|
| 実現可能性(難易度) | 技術的な実現性、社内リソース確保可否 | 難易度が低めのものから着手したほうが成功体験を得やすい。 |
| インパクト(効果量) | コスト削減、売上拡大、業務効率向上 | 小さくても効果の見えやすいものを早く動かす。 |
| リソース投入量 | 人材、時間、予算 | 低リソースで済むものから始めて“力技”で進めすぎない。 |
| リスク度 | システム停止、従業員反発、法規制影響 | リスクが低めな領域を最初に手がける。 |
| 拡張可能性 | 他部門展開や発展性 | 一度やった成功を他へ横展開できるものが望ましい。 |
これらを勘案して、以下ような段階的ステップで進めると理想的です。
フェーズ別の着手優先領域(例)
以下は一例です。各社でアレンジが必要ですが、ひとつの参考になるフェーズモデルとしてご覧ください。
| フェーズ | 着手領域例 | 目的・ポイント | 人材育成会社が果たせる支援 |
|---|---|---|---|
| フェーズ0(準備) | DXビジョンの共有・合意形成 | 全社でDXの意義・目的を共通化する | 経営層ワークショップ、勉強会設計、キックオフ支援 |
| フェーズ1(業務改善型) | 定型業務のデジタル化・自動化(RPA、OCR、勤怠・経費精算など) | “小さく早く”成果を出して社内の信頼を得る | 業務プロセス可視化支援、操作研修、定着支援 |
| フェーズ2(部門横断型) | 部門間データ連携、BI(分析基盤構築)、データ活用の初歩 | 部門をまたいだ改善やデータ経営の基礎をつくる | データ分析教育、ハンズオン演習、事例共有 |
| フェーズ3(ビジネス変革型) | 新規サービス開発、ビジネスモデルの変革、AI/IoT活用 | 本質的な変革を狙い、競争優位を作る | アジャイル型開発支援、PoC構築支援、社内人材育成連携 |
| フェーズ4(拡張・最適化) | 継続的改善、全社横展開、DXガバナンス整備 | 成果を持続させ、DXが組織文化になる段階 | 振り返り・改善支援、DX人材育成体系、組織設計支援 |
このように、「小さく動かして勝ちパターンを示してから拡張する」のが安全かつ説得力のある進め方です。
人材育成会社としては、教育設計、プロジェクト支援、変革期対応支援などをDXの初期段階から組み込んでいくことが有効です。
他社の取り組み事例から学ぼう
製造業
● ダイキン工業(実績ベース)
空調機器をIoT化し、「DK-CONNECT」などで稼働状況をクラウド経由で一元管理。遠隔監視・保守を可能にし、メンテナンスコストの削減や業務効率化に貢献しています。
出典:日経クロステック
● パナソニック(報道ベース)
電気シェーバーの設計に生成AI(ジェネレーティブデザイン)を導入し、従来より高性能かつ短期間での開発を実現したと報じられています。
出典:日経ビジネス
建設業
● 清水建設(実績ベース)
建設現場のデータや設備情報をAPIで連携する「DX-Core」を開発。設計・施工・維持管理の効率化を目指し、BIMとの連携も進めています。
出典:清水建設公式サイト
● 戸田建設(報道ベース)
AIカメラで現場点検業務を自動化。動画から異常検知をAIが行い、作業時間の約90%削減を実現したと報じられています。
出典:建設通信新聞
サービス業・物流
● 日本通運(実績ベース)
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)導入により、定型業務で年間72万時間の作業時間削減を達成。UiPath導入事例としても詳細公開されています。
出典:日本通運公式
追加出典:UiPath導入事例
● ファミリーマート(実績ベース)
外国籍スタッフの在留カード確認業務にIC読み取りアプリを導入し、店頭での手続き時間を大幅短縮。採用の効率性と法令順守を両立。
出典:デロイトトーマツ
金融
● 三菱UFJ銀行(報道・試算ベース)
社内にChatGPTベースの「AI上司」システムを導入し、社内文書作成・稟議書ドラフトの効率化などで、月22万時間の業務削減効果を見込むとされています(ただし、具体的な公式数値発表は現時点ではなし)。
出典:AI総研(メタバース総研)
補足記事:ONEWORD
これらの事例は、「時短=DXの実感しやすい効果」であることを示しています。
時短効果を出すためのIT系人材育成研修会社の関わり方
・操作方法のレクチャーやマニュアル作成
・現場社員向けの実践的研修
・「どれくらい時間が減ったか」を見える化して共有
・成功事例をテンプレ化して横展開しやすくする
・導入後に継続的なサポート体制をつくる
「ツールを入れて終わり」ではなく、「社員が活用して初めて意味がある」という考え方が大切です。
これら事例から見えてくる共通点と学びを、次章で整理します。
事例から引き出せる成功要因と注意点
事例を見て「いいなあ」「うちもできそう」と思っても、実際導入すると躓くことも多いです。以下に“成功のカギ”および“失敗・注意すべき点”を整理します。
成功要因(共通パターン)
- トップの強いコミットメント
経営層が旗振りしないと、DXは「IT部門の仕事」にとどまり、全社化しません。 - スモールスタートで成功体験を積む
最初から大規模改革を狙うと失敗リスクが高い。定型業務や局所的な領域から始めて「確実に成果を出す」。 - 部門横断での協業体制
IT部門だけでなく、業務部門・営業部門などを巻き込む形で進める。 - 人材育成と現場定着を同時に設計
技術(ツール)導入だけでなく、現場社員が使えるように育て、運用に落とし込む。 - 改善の継続とフィードバックループ設計
導入後に運用をチェックし、改善を重ねていくPDCA型の設計。
注意点・失敗しやすい点
- 目的と手段の逆転
DX導入=「いいツールを入れればいい」と考えると、本来の目的(業務革新、顧客価値向上)が置き去りになる。 - 既存業務をそのままデジタル化
“無駄な業務プロセスをそのまま再現してしまう”ことが多い。業務そのものを見直すことが不可欠。 - 現場の抵抗・不満を軽視する
不安を抱く社員への説明、巻き込み、交渉が疎かだと、DX導入後放置される。 - 予算・リソースの過小見積もり
想定外のコストや人的負荷が膨らみ、途中で挫折すること。 - ガバナンス・統制設計不足
データの品質管理、利用ルール、権限設定、責任分担が曖昧だと混乱が起きる。
総合的なおすすめ優先戦略(人材育成会社視点)
人材育成会社としてDX支援をするなら、以下のような優先戦略をとるといいと思います(もちろん、クライアント企業ごとの調整は必要ですが…)。
- DX意識を高める啓発・共通言語づくり
まずは経営層・現場にDXとは何かを伝え、なぜやるかを言語化して合意を作る場を設ける(ワークショップ、勉強会、事例紹介など)。 - 現状業務可視化+“痛みポイント(非効率領域)”抽出
業務フローをヒアリング・可視化して、無駄・遅延箇所を洗い出す。そこを改善候補にする。 - 小さな実験プロジェクト(PoC)を立ち上げる
たとえば定型業務の自動化や、データダッシュボード導入など、短期間で成果が出せそうなプロジェクトを選ぶ。 - 教育設計と実践連携
ツール導入と同時に、現場社員向け操作研修、使い方フォロー体制を設計する。OJTやメンタリングを組む。 - 振り返り・改善 → 横展開
PoCから得た知見を振り返り、改善してから他部門や領域に広げる。 - DXガバナンス・組織体制整備
DX推進責任者、部門横断チーム、評価指標、定期レビュー体制を整える。 - 中長期的なビジネス変革を視野に入れる
最初は業務改善型だとしても、ゆくゆくは新サービス・ビジネスモデル変革を狙える領域も視野に入れておく。
まとめ(振り返りと今後の学習指針)
いかがでしたか?いくつかポイントをまとめますね 😊
- DXが遅れる原因は、「技術課題」だけでなく「人材・文化・意思決定プロセス・制度環境」など多面的な要因が絡む
- 人材育成会社視点では、「変革を導けるリーダー育成」「現場巻き込み」「教育→実践の連結」が鍵
- 着手すべきは、まず“成果が出しやすく、リスクが比較的低い領域”から手をつけ、成功体験を作ること
- 他業界の事例(製造、建設、小売、金融など)を見て、「この業界ならこうアプローチできるな」というヒントを得る
- 成功には、教育+実践+改善というサイクルを設計することが不可欠
今後の学習指針として、次のようなステップをおすすめします:
変革リーダー育成・チェンジマネジメント に関する理論・実践を深め、現場抵抗や心理的な壁を乗り越える技を持つ
DX成熟度(デジタルマチュリティ)モデル を学び、自社・顧客企業の現在地点を評価できるようにする
業務プロセス可視化手法(BPMN、業務フロー図、Value Stream Mappingなど) を使えるようにする
データ活用/BI/AIの基礎知識 を学び、実践的な使いどころを考えられるようにする
アジャイル/リーン型プロジェクト手法 を身につけ、変化対応力を持たせる
にゃんこエピソード
ちょっと和む話をひとつ。
あるクライアント企業で、社員向けにDX研修を実施したときのことです。
研修の合間に休憩をとっていたら、開けっぱなしの会場ドアから近所の猫ちゃんがすっと入ってきて、講師の前を通過してプロジェクターの前に。
なんと、映し出されていたスライドが、にゃんこの影で一瞬だけ消えてしまいました。
すると講師が、「DXで言えば“予想外の邪魔”にも落ち着いて対応できる柔軟性が大切ですよね」と、笑いを交えつつ話を展開。
緊張していた参加者の顔が一気にゆるみ、会場が温かい空気に包まれた瞬間でした。
にゃんこって、本当にタイミング読めるんですよね。
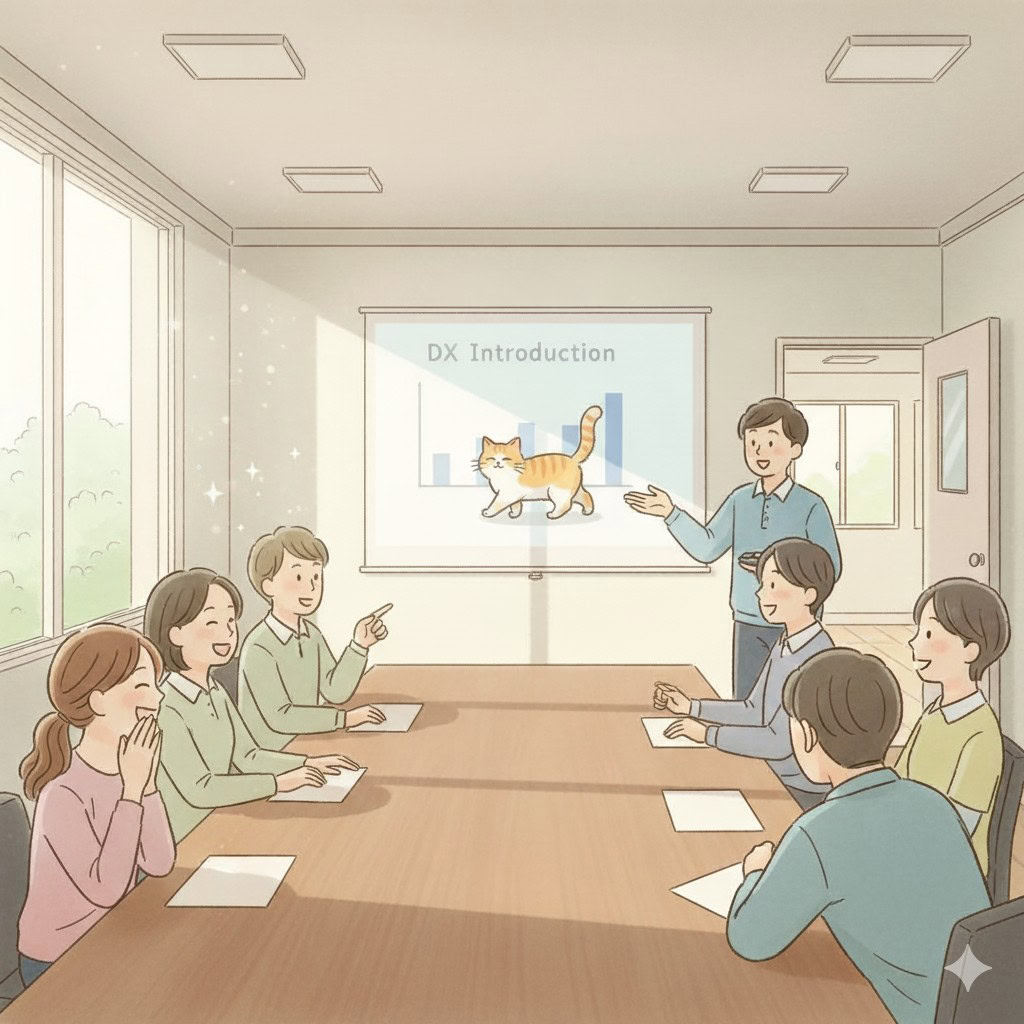
私たちセイ・コンサルティング・グループでは、様々な学びを提供しております。
▶IT企業向け新人研修のおすすめ内容(2025)
▶おすすめの研修内容
投稿者プロフィール

-
セイ・コンサルティング・グループ株式会社専務取締役
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上
キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
アンガーマネジメントファシリテーター、コンサルタント
ハッピーな人生を送る秘訣は「何事も楽しむ!」ことにあり。
一期一会を大切に、そして楽しく笑顔になる研修をミッションに!




