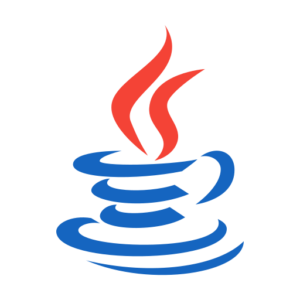JavaScriptの歴史を理解して、コードに深みを持たせよう
こんにちは。ゆうせいです。
普段からJavaScriptを書いていると、constやPromise、async/awaitなどの機能を自然に使っていると思います。でも、こんな風に感じたことはありませんか?
- 「なんで昔は
varばっかりだったんだろう?」 - 「
==と===の違いって、そもそもなにが背景なの?」 - 「jQuery全盛期って、いったい何が起こってたの?」
JavaScriptは「とりあえず動く」コードが書けてしまう分、歴史を知らずに習得できてしまう言語です。
でも、歴史を知ると「なぜ今の仕様になっているのか」が見えてきて、より“意識の高いコード”が書けるようになります。
さあ、JavaScriptがどのように進化してきたのか、一緒に時代をさかのぼってみましょう!
JavaScript誕生:わずか10日で生まれた言語
1995年:Netscape Navigatorに組み込まれる
JavaScriptは、Brendan Eich(ブレンダン・アイク)が1995年にたった10日間で作り上げたスクリプト言語です。
当初の目的は次のようなものでした:
HTMLと連携して、動きのあるインタラクティブなWebを実現する
この初期のJavaScriptは、今のような「万能言語」ではなく、フォームのバリデーションやアラート表示ができればOKという位置づけでした。
alert("こんにちは!");
ちなみに、当初は「Mocha」という名前で開発され、途中で「LiveScript」、そして「JavaScript」へと改名されました。
Javaとの関係は?
名前に「Java」が入っていますが、実際のところ関係はほとんどありません。
これは「Java人気にあやかるためのマーケティング戦略」だったのです。
標準化とIEとの戦い:ECMAScript登場
JavaScriptの仕様が乱立しないよう、1997年にECMA(ヨーロッパ電子工業標準化機構)が登場し、ECMAScriptという標準仕様が定義されます。
ECMA-262(ES1〜ES3)
- ES1(1997):最初の標準仕様。基本的な構文と制御フロー
- ES2(1998):ISO準拠の微修正
- ES3(1999):
try/catch、正規表現、switchなどが追加される
この時代のブラウザは「IE6 vs Netscape」という熾烈な競争の中で、互換性のない独自実装が多発しました。
JavaScriptの不安定な印象が残るのは、この頃の名残です。
停滞期とjQueryの時代(2000年代前半〜中盤)
ES4の失敗と混乱
2000年代に入り、ECMAScript 4(ES4)の開発がスタートしますが、提案が複雑すぎたために挫折します。
その代わりに、Webの世界ではjQueryが台頭。
$(".btn").on("click", function() {
alert("クリックされた!");
});
- クロスブラウザ対応が簡単
- DOM操作が直感的
- Ajaxが簡潔に使える
当時は「JavaScript ≒ jQuery」だったと言っても過言ではありません。
ES5(2009):構文の整備と「脱カオス」の第一歩
jQuery全盛期の裏で、JavaScript自体も静かに進化していました。
ES5の主な追加機能
strict modeによるエラーの厳格化Object.create、Object.definePropertyArray.prototype.forEach,map,filterなどの高階関数JSON.parse()とJSON.stringify()
"use strict";
let arr = [1, 2, 3];
let doubled = arr.map(n => n * 2);
ES5は、JavaScriptを安全で予測可能な言語へと進化させるための基礎工事でした。
ES6(2015):“モダンJavaScript”の始まり
ついにJavaScriptが大改革を迎える年が来ます。ES6(またはES2015)の登場です。
主な進化ポイント
let/const- アロー関数
() => {} - クラス構文
class - モジュール
import/export Promise- テンプレートリテラル
`文字列${変数}` - 分割代入、デフォルト引数、スプレッド演算子
const greet = name => `こんにちは、${name}`;
これまでの「レガシー言語」の印象を打ち破り、モダンな開発言語として世界中に認知されるきっかけとなりました。
それ以降:毎年進化するJavaScript(ES7〜現在)
ES6以降、JavaScriptは毎年アップデートされる「Living Standard」となりました。
主な機能の追加履歴
| 年 | 機能例 |
|---|---|
| ES2016 | Array.prototype.includes()、指数演算子 ** |
| ES2017 | async/await、Object.entries() |
| ES2018 | スプレッド演算子のオブジェクト対応、非同期イテレータ |
| ES2019 | flat(), flatMap(), optional catch binding |
| ES2020 | Null合体演算子 ??、オプショナルチェイニング ?. |
| ES2021〜25 | Promise.any, at(), Record & Tuple, Temporal, pipeline operator など |
このように、新しい構文・ユーティリティ関数が毎年少しずつ追加されることで、JavaScriptは「書きやすく・読みやすく・壊れにくい」言語へと進化してきました。
歴史を知るメリット
過去を知れば「なぜこう書くのか」がわかる
varを使うと巻き上げ(hoisting)で混乱しやすい==が型変換を行う仕様でトラブルを引き起こすPromiseがなかった頃、コールバック地獄に悩まされていた
現代のJavaScriptの“良さ”や“注意点”は、過去の失敗や制限からの脱却によって生まれているのです。
今後の学習指針
JavaScriptの歴史を理解した今、次に学ぶべき方向は以下のようになります。
- 非同期処理の進化(Promise → async/await → Signal & Task)
- 構文糖衣(syntactic sugar)の背景と落とし穴を理解する
- JSエンジンの内部(V8やSpiderMonkey)を学ぶ
- 新仕様(Record/Tuple、Type Annotations)にアンテナを張る
- 仕様策定の場(TC39)や提案の流れに触れる
JavaScriptは、10日で生まれ、混乱を乗り越え、今ではWebだけでなくサーバー、IoT、AI領域にまで使われる「汎用スクリプト言語」に成長しました。
コードを書くたびに、その背景にある“歴史”も感じながら、より深い理解を目指してみてください!
セイ・コンサルティング・グループの新人エンジニア研修のメニューへのリンク
投稿者プロフィール

- 代表取締役
-
セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
すべての無駄を省いた費用対効果の高い「筋肉質」な研修を提供します!
この記事に間違い等ありましたらぜひお知らせください。
学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。
最新の投稿
 新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの? コピー
新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの? コピー 新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの?
新人エンジニア研修講師2026年2月28日f(x, y) とf(x; y) って何が違うの? 新人エンジニア研修講師2026年2月28日AIの深層へようこそ!逆伝播バックプロパゲーションの仕組みを完全マスター
新人エンジニア研修講師2026年2月28日AIの深層へようこそ!逆伝播バックプロパゲーションの仕組みを完全マスター 新人エンジニア研修講師2026年2月28日機械学習で必須のscikit-learn関数ベスト10
新人エンジニア研修講師2026年2月28日機械学習で必須のscikit-learn関数ベスト10