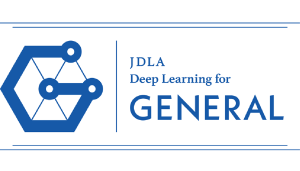中小企業も「多角化経営」を考える時代へ
これまでは、「まずは本業をしっかり」が中小企業の鉄則とされてきました。
でも、最近は少しずつ潮目が変わってきています。
たとえば、技術の進化や顧客ニーズの変化、そして予測しづらい社会情勢(パンデミックや物価高騰など)。
こうした変化に対応するには、1つの事業だけに依存しない体制が大切なんですね。
では、多角化ってどんな方法があるんでしょう?
わかりやすく分けてみました。
多角化経営の代表的なスタイル
既存事業との「シナジー型」多角化
今のビジネスの延長線上にある新たなサービスや商品を展開するタイプです。
例:IT人材育成研修会社の場合
- オンライン講座プラットフォームの運営
→ 自社で作った講座を販売するだけでなく、他の講師にも提供して展開。 - 企業向けDXコンサルティング
→ 人材育成の知見を活かして、企業全体のデジタル推進をサポート。 - 採用支援サービス
→ 育成した人材を「就職・転職」までつなげる事業。就職エージェント的役割。
メリット:今のノウハウが活かせる!
デメリット:競合が多くなりやすい。
異業種への「チャレンジ型」多角化
まったく新しい業種へ挑戦するスタイルです。リスクは高いですが、うまくいけば収益の柱がもう1本できます。
例:IT人材育成研修会社が異業種にチャレンジする場合
- eスポーツ事業
→ プログラミング人材と親和性が高い若者向けマーケット。 - シニア向けスマホ教室事業
→ 高齢化社会でニーズが増加中。「人に教える」ノウハウを転用。 - 教育マンガ・アニメ制作
→ ITの難しい内容を「マンガで解説」。親しみやすく広がりやすい!
メリット:新たな市場を開拓できる
デメリット:初期投資やノウハウ構築が必要
他業種の中小企業での多角化事例
飲食業
例:居酒屋が「冷凍食品の通販」を開始
コロナ禍で店舗の来客が激減したことをきっかけに、自慢のメニューを冷凍食品として販売。ECサイトやAmazonでも展開!
→ メリット:既存の商品力を生かせる
→ デメリット:物流や製造ノウハウの習得が必要
建設業
例:リフォーム会社が「DIY教室」や「資材販売」を展開
リフォームに興味のある人を対象に、ワークショップを開催したり、資材を自社倉庫から小口販売したりしている事例も。
→ メリット:顧客との接点を増やせる
→ デメリット:マーケティング力が必要
にゃんこエピソード:ヒントはにゃんこから!?
あるIT研修会社のAさん。自宅のにゃんこが、ある日パソコンの上にドーン!と座ったそうです。
「こらっ!お客さんの資料作ってるとこなのに~」
でも、そのときふと気づいたんです。
「うちの教材、猫みたいに“ぬくもり”が足りないかも?」と。
そこから始まったのが「癒し系キャラがナビゲートするIT研修動画」!
結果、受講者の離脱率がグッと減ったとか…!
にゃんこ、さすがです(ΦωΦ)
多角化で成功するためのポイント
- 自社の強みをしっかり分析する
- 小さく始めて様子を見る(スモールスタート)
- 信頼できるパートナーとの連携を考える
- 補助金や助成金を活用する(意外と多角化向けの制度あります!)
まとめと、これからの学習の指針
中小企業にとっての多角化経営は、「生き残りの手段」ではなく「新しい価値創造の道」でもあります。
いきなり大きな転換をするのではなく、まずは自社の強みをベースに、少しずつ「可能性の芽」を育てていくことが大切です。
これから勉強すると良いテーマはこんな感じです:
- 「シナジー効果とは何か?」
- 「異業種進出の成功事例」
- 「デジタルを活用した多角化戦略(EC、動画、SNS)」
- 「中小企業向け補助金の探し方」
あなたの会社も、次の一歩がすぐそこかもしれませんよ!٩( 'ω' )و
もし気になるアイデアや「もう少し詳しく聞きたい!」ことがあれば、ぜひ教えてくださいね♪

私たちセイ・コンサルティング・グループでは、様々な学びを提供しております。
▶IT企業向け新人研修のおすすめ内容(2025)
▶おすすめの研修内容
投稿者プロフィール

-
セイ・コンサルティング・グループ株式会社専務取締役
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上
キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
アンガーマネジメントファシリテーター、コンサルタント
ハッピーな人生を送る秘訣は「何事も楽しむ!」ことにあり。
一期一会を大切に、そして楽しく笑顔になる研修をミッションに!